近年、ChatGPT や Claude、Gemini などの生成 AI が、急速に仕事の現場に浸透しています。文章作成やリサーチ、コードレビュー、資料のドラフト作成など、AI が自然な言葉で助けてくれる時代になりました。一方で、AI の「本当にできること」と「できそうに“見えてしまう”こと」のあいだには、依然として大きなギャップがあります。たとえば「AI は言葉の意味を理解している」「幻覚(ハルシネーション)はプロンプトで防げる」といった考え方は、実はどれも誤解を含んでいます。この記事では、生成 AI に関する代表的な 10 の誤解を取り上げながら、生成 AI を正しく理解するための視点をお伝えします。
目次
はじめに:AI は「理解しているように見える」だけ
生成 AI は、人間のように考えたり、理解したりしているわけではありません。AI がしているのは「次に来る単語を予測する」こと。つまり、過去の文章パターンの統計をもとに、確率的に言葉を選んでいるのです。その結果として、出力される文章が人間にとって自然に見えるため、あたかも「AI が意味を理解している」と感じてしまいます。この現象は、研究の世界ではポチョムキン理解(Potemkin Understanding)と呼ばれます。見た目は立派でも中身が空っぽな“ポチョムキン村(Potemkin Village)”の比喩で、整合した説明を返すが、内部で命題を意図的に操作している保証はない状態を指します。
「生成 AI は検索エンジンやデータベースの代わりになる」
多くの人が勘違いしやすいのが、AI が最新情報を「知っている」という点です。実際には、生成 AI はあらかじめ学習したデータに基づいて文章を作っています。たとえば、学習が 2023 年までなら、それ以降の出来事や法律の改正、製品情報などは知らないままです。このような、モデルの学習に使われたデータの最新時点を示す期日のことをカットオフ(cutoff: モデルが学習した“知識の最終更新日”)と言います。カットオフ以降の情報は、モデルは学習していないため、そのままでは正確には回答できません(推測でもっともらしい文章を生成することはあります)。その限界を補う仕組みの一つがRAG(Retrieval-Augmented Generation)と呼ばれる技術です。これは、AI が答える前に外部のデータベースを検索し、その結果を文章生成に組み込むという仕組みです。ただし、RAG を導入しても、検索結果が正確でなければ誤情報をそのまま出力するリスクがあります。RAG は“魔法のアップデート機能”ではなく、検索・整形・統合の精度を高める設計手法と理解するのが正確です。(RAG の設計要素については後述の「3. RAG を使えば~」でも触れます。)
「AI は人間のように論理的に考えている」
現在主流の大規模言語モデルは、内部で精緻な表現を形成しているものの、人間のように命題的意味を「前提→論理操作→結論」という手続きを“意図して”操作しているとはまだ言い切れません。本質的には 連続する次語予測の連鎖 により、訓練分布に統計的に整合する文章を再構成しているに過ぎません。人間の推論が明示的な因果ステップを辿るのに対し、モデルは似たパターンの再現結果として「論理的に見える」文章を出力しています。この差異を理解しておくと、出力を鵜呑みにせず補助的に活用できます。複雑な数式推論や高リスク判断は、外部ツール(数式ソルバ / コード実行 / ルールエンジン)との分業で信頼性を底上げします。AI は「思考エンジン」よりも「説明生成インタフェース」と捉えると最も力を発揮します。
「RAG を使えば“最新で正確”な結果が得られる」
RAG を導入すれば、AI が外部情報を活用できるようになりますが、それでも情報の正確性は検索精度に依存します。検索対象の文書が古い、曖昧、あるいは誤っていれば、AI の出力も当然間違います。RAG の品質を決めるのは、検索の「粒度」や「文書分割(chunking)の戦略」、埋め込みモデル選定、再ランキング、そして どこまで AI に任せどこから人間/ルールで制約するか という編集方針です。「情報をどう選び、どう結合するか」という人間側の設計が、AI の信頼性を左右します。RAG とは、AI を最新化する装置ではなく、知識を外部に切り離して管理するための設計思想であるといえます。
「同じプロンプトなら同じ答えが出る」
AI の出力は確率的に生成されるため、同じ指示でも毎回微妙に違う結果になります。これは不具合ではなく、AI が“多様な可能性”を持っている証拠です。たとえば、創造的な文章を出したいときは「温度(temperature)」を上げたり、「top_p(核サンプリング)」の値を広げるとバリエーションが増えます。逆に、業務マニュアルのように安定した回答が欲しい場合は温度や top_p を下げ、出力の揺れを抑えます。AI を安定して使うには、「どこまでの揺らぎを許容するか」を設計段階で決めておくことが大切です。
「大きなモデルほど性能が高い」
モデルのサイズが大きいほど高性能、というのは半分正解で半分誤解です。パラメータ(AI の内部の学習要素)を増やせば表現力は上がりますが、計算コストや応答速度、データ品質とのバランスが崩れると逆効果になることもあります。近年では、必要なときだけ特定の専門モデルを呼び出す Mixture of Experts(MoE: 専門家混合モデル) という考え方も広がっています。「より大きく」ではなく、「より適切に使い分ける」ことが、AI 活用の次のステージといえます。
「幻覚(ハルシネーション)はプロンプトで防げる」
幻覚とは、AI がそれっぽいけれど事実ではない情報を出してしまう現象のことです。これはモデルの仕組み上、現在の主流アーキテクチャでは完全に防ぐことはできません。AI は「確率的にもっとも自然な文章」を選んで出力しているため、時には“もっともらしい誤り”を生み出します。対策としては、AI の出力を 検証→隔離→再試行 できる構造を設計することが現実的です。よくある幻覚例と、それに対応する設計パターンを挙げます:
典型的な幻覚例:
- 実在しない論文・書籍の引用生成
- API の存在しないメソッド / 引数の捏造
- 製品仕様や法令の“最新”と称した誤情報
- 数式計算の桁ずれや単位変換の誤り
緩和パターン:
- 出典 / 参照リンク(取得元文書ID)を必須フィールド化し、欠落時は再生成
- 二段階モデル(生成 → 別モデルで事実性 / 根拠一致率評価)
- 根拠文書抜粋(引用スニペット)と回答の語彙オーバーラップ率計測
- 高リスク領域(法務 / 医療 / 財務)はルールベース検証 or 人間レビュー必須ゲート
運用 KPI の例: 支持文書一致率、引用欠落率、再生成率、ハルシネーション検出精度(人手評価との一致)。幻覚はバグではなく「仕様の一部」と理解し、“一定割合で誤りが混ざる”前提から逆算して どこで検出し隔離し再試行するか を決めることが本質です。
「ベンチマークが高ければ“理解”している」
AI の性能を測る指標として、MMLU や GSM8K などのベンチマークスコアがよく使われます。しかし、これらは特定の形式のテストに慣れているかどうかを測るものであり、汎用的な理解力を保証するものではありません。問題の言い回しを少し変えるだけで正答率が大きく下がるケースもあります。(これは前述した「統計的再現」に起因する現象です。)このように、AI が「理解しているように見える」のは、実際には パターンを暗記し再構成しているだけ であることが多いのです。
「プロンプトを工夫すれば万能になる」
プロンプトとは、AI に与える「指示文」のことです。工夫すれば出力の質は確かに向上しますが、プロンプトで新しい知識を生み出すことはできません。プロンプトができるのは、AI がすでに持っている知識を「どう引き出すか」を最適化することです。また、プロンプト設計だけに頼ると、AI に任せてはいけない判断まで委ねてしまうことがあります。信頼性を高めるには、プロンプトに加えて、出力を検証・再実行・再評価する仕組み(例: 評価ループ / 自動テスト用プロンプト / ルールエンジン) を整える必要があります。
「ファインチューニングすれば自由に作り変えられる」
ファインチューニングとは、既存の AI モデルに追加学習を行い、特定分野に特化させる技術です。たとえば社内マニュアルや顧客対応データを学習させることで、社内用 AI を作ることができます。ただし、過度なファインチューニングは過学習(特定のデータに偏りすぎる現象)を招く恐れがあります。また、一度学習した知識を上書きすると、もとの汎用能力が失われることもあります。最近では、知識をモデルの外部に置き、AI は必要なときだけそれを参照する「軽量適応(LoRA / Adapter / Prefix Tuning など)」や「RAG」のほうが現実的です。
「AI の仕組みは完全なブラックボックス」
AI の内部は複雑ですが、まったく見えないわけではありません。どの単語や文脈に注目して出力を作っているのかを解析する研究(Attention パターン解析、勾配帰属法〈Integrated Gradients など〉、中間表現クラスタ、回路レベル解析)が進んでいます。これを 解釈可能性(Interpretability) と呼びます。たとえば、AI がどの部分の文章を根拠に回答を作ったのかを可視化することで、「なぜこの結果になったのか」を部分的に説明できます。ただし、これらは局所的説明であり モデル全挙動の完全説明には未到達 という限界も明示しておく必要があります。この取り組みは、AI を業務に組み込む上での信頼性・説明責任(Accountability)・監査性を高める重要な要素です。
まとめ:「信じる」より「設計する」
生成 AI は、魔法のように賢い存在ではありません。しかし、限界を前提にアーキテクチャと運用プロセスを設計すれば、業務効率と知的作業のスループットを飛躍的に高める強力なツールになります。観測可能な指標にもとづいて改善を回すことで、生成 AI は私たちの仕事を確実に支えるパートナーになっていきます。どう設計すれば安全かつ再現性を持ってAIを使えるかを考えることが今後の課題となっていくでしょう。

![devlog [開発部門ブログ]](https://devlog.neton.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/logo.png)
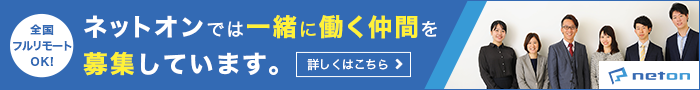
-160x160.png)