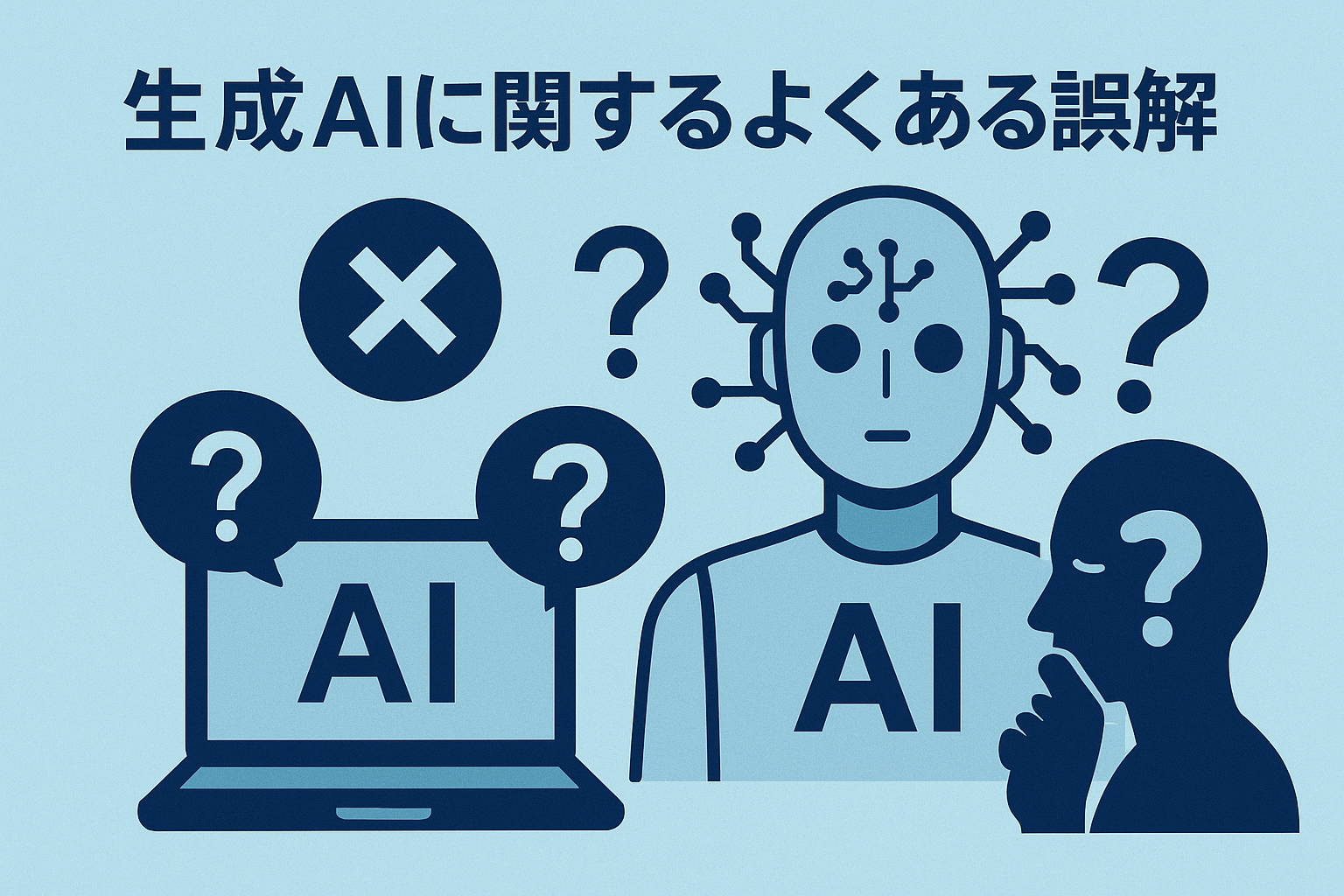目次
はじめに
今回は前々から気になっていた著者:牛尾剛さんの書籍「世界一流エンジニアの思考法」を読んだので、自分なりの要約と良かった所の感想をブログで紹介できたらと思います。
この書籍を読むことで、生産性を上げるテクニックや成果を出し続ける思考法など学ぶことができます。
ITエンジニア本大賞2025年度でもビジネス書部門ベスト10・特別賞にも上がっているので、気になっている方は手に取ってみてもいいと思える良本だと思います。
本書の概要とポイント
本書は著者の牛尾剛さんが米マイクロソフトで働く中で目の当たりにした、トップエンジニアたちの圧倒的なパフォーマンスの秘密について紹介しています。
今回は各章ごとに要約と私が感じたことを書いていきたいと思います。
この章では、著者の牛尾さんがマイクロソフトで出会ったトップエンジニアたちの問題解決アプローチが紹介しています。
彼らトップエンジニアの特徴は、やみくもに手を動かさないこと。
問題に直面したとき、まずログなどの事実(ファクト)を一つだけ見て仮説を立て、その仮説を証明するためだけの最小限の行動をとります。
対して、著者が以前行っていたような、思いつきで様々な可能性を試す「試行錯誤」は、時間と労力を浪費するだけで成長につながらない「悪」だと書かれています。
また、「頭はよくても『理解』には時間がかかる」とも書かれており、トップエンジニアと呼ばれる方々も理解には時間をかけて基礎を積み重ねているという事実を受け入れ、焦らずに基礎をじっくり学ぶことの重要性が書かれていました。
私も普段業務で問題や不具合が発生した際は牛尾さんと同じように「試行錯誤」をするタイプなので、「悪」な行動を取ってました…。
もちろんログやデータを収集はしてあたりをつけてましたが、結局はあそこかな?こっちかな?と可能性を潰していく手段をとっていたので、効率の悪い行動を取ってましたね…。(;一_一)
今後の行動方針の参考にさせていただこうと思いました。
ここでは、生産性を加速させる3つのマインドセットが紹介されます。
- Be Lazy(怠惰であれ)
- やるべきことを「一つだけ」に絞り、最小の労力で最大の価値を生むことに集中する。
- リスクや間違いを快く受け入れる
- 「Fail Fast(早く失敗する)」の精神で、失敗を学びの機会と捉える。
- 不確実性を受け入れる
- 緻密な計画に固執せず、状況の変化に柔軟に対応する。
これらのマインドセットは、日本の「あれもこれも完璧に」という文化とは対極にありますが、変化の速い現代において非常に重要な考え方だと思いました。
日本と米国での仕事の考え方の違いに驚きました。
特にやるべきことの優先順位の付け方はまさに書かれてる通りで、重要なタスクに優先順位をつけてどう「すべて終わらせるか?」を私も考えてました。
ここはお国柄というのもあるので真似るのは難しそうですが、それでも「一番インパクトのある一つ」を見極めてそれを確実に行うという行動は今後の行動に取り入れることは可能なので、見習っていこうと思います。
生産性を上げるには、脳のCPUを無駄遣いしないことが重要で、この章ではそのための具体的な方法が紹介されています。
- コードリーディングのコツは、極力読まないこと
- すべてを読もうとせず、インターフェースと構造の理解に集中する。
- マルチタスクはしない
- 人間の脳はマルチタスクに向いていない。「WIP=1」(仕掛中の仕事は1つ)を徹底する。
- 一日4時間は自分だけの時間を確保する
- チャットやメールを遮断し、最も重要な仕事に集中する時間を意図的につくる。
- 記憶力の正体は「理解の深さ」
- 人に説明できるレベルまで深く理解し、構造化(メンタルモデル化)することが記憶の定着につながる。
私、
- PRとかコードは全て読もうとする(読まないと意図が正確に理解できないから…)
- マルチタスクやりがち(あれこれ気になって目移りしがち…)
- 自分だけの時間の確保が出来てない(チャット・メール・MTG・その他などで自分だけの時間を確保するという考えが薄い)
- その場での理解はしているが、記憶の定着までは出来てない
と、紹介されてる内容の行動が全然取れてないことが改めて実感しました…。
「マルチタスク」「自分だけの時間確保」「記憶力向上」などは普段の業務の取り組み改善で習慣化していこうと思いますが、「コードリーディング」の改善は業務コードのリファクタリングも視野に入れて長期的に改善に取り組む必要がある課題になりそうなので、出来ることからコツコツしていこうと思います。
エンジニアの仕事はコミュニケーションの塊です。
この章では、円滑なコミュニケーションで生産性を上げる方法が紹介されています。
- 情報量を減らす
- 一度に伝える情報は最小限にする。相手から聞かれたら追加で説明するスタイルが効果的。
- クイックコールを活用する
- テキストのやり取りで時間がかかる問題は、すぐに短いビデオ通話で解決する。
- 意見が対立しても「否定しない」
- 「In my opinion(私の意見では)」という枕詞を使い、相手を尊重しつつ自分の意見を伝える。
- ディスカッションは学びの場
- 勝ち負けではなく、知識を深める機会と捉え、知らないことは臆せず質問する。
私も例に漏れず、情報量が多いチャットやコミュニケーションを取ってしまいがちです。
自分の持ってる情報はできる限り共有しようという考えなんですが、情報量が多いことで書くことはもちろん理解する時間もかかるので、相手に対しても負荷が高めになるという自覚はあるので、この辺実践していこうと思います。
個人の生産性だけでなく、チーム全体の生産性を高めるためのマネジメントスタイルについて解説されます。
- サーバントリーダーシップ
- リーダーの役割は、指示命令ではなく、メンバーをサポートし、障害を取り除く(アンブロックする)こと。
- 自己組織チーム
- チーム自身が意思決定を行うことで、スピードとエンゲージメントが高まる。
- 失敗に寛容な文化
- 心理的安全性を確保し、誰もが安心して挑戦できる空気を作ることがイノベーションを生む。
マネージャとしての考え方やあり方について書かれており、どれだけサポートができるかが生産性を高めるために重要かを解説してくれていました。
個人的に気になった点はサーバントリーダーシップ制のマネージャが重視するのはメンタル面で、「仕事を楽しんでいるか?」を確認する文化という点に興味がありました。
確かに普段業務をしてて私は仕事をしているのであって、「仕事を楽しんでいるか?」と問われると、「うーん…普通で特に意識してないなぁ…」という答えになってしまいます。
(いやプログラム書いたり調査したりは楽しいので、嫌じゃないですよ?)
仕事=楽しいと結びつけること自体があんまり意識してなかったので、新しい観点だなと思いました。
今後の仕事に対しての考え方に取り入れようと思います。
※楽しいに越したことはないからね!
高いパフォーマンスは、健全な生活習慣から生まれます。この章では、心身のコンディションを整えるための具体的な方法が紹介してくれています。
- タイムボックス制
- 時間を区切って仕事を強制的に終了させ、学習やプライベートの時間を確保する。
- 脳の酷使をやめる
- 瞑想、睡眠、ディスプレイから意識的に離れる ことで脳をしっかり休ませる。
- 掃除で「完了」の感覚を掴む
- 身の回りを整理整頓することで、頭の中も整理され、「人生をコントロールできている感覚」を取り戻す。
- 身体のメンテナンス
- 筋トレや有酸素運動で、気力と体力の低下を防ぐ。
仕事柄インドアな生活になりがちではあるので、健全な生活習慣が送れていないことや、睡眠時間がバラバラで最近睡眠不足を感じていたのでこの章は改めて身体が資本ということを意識づけさせてくれました。
(休日にはサイクリングに行きますが、昔に比べて確実に頻度落ちているので身体が鈍っています💦)
また「掃除で「人生をコントロールする感覚」を取り戻す」話が面白かったです。
私掃除が苦手…というか整理が苦手です。
結構身の回りの整理は適当にまとめている程度です。
最初読んだ時、「掃除で…?」と思いましたが、読み進めていくと、「身の回りの整理」→ 「情報の整理」→「頭の中の整理」と整理の段階の解説があり、整理の質が上がれば作業効率も上がることが書かれていました。
PCのファイル・ドキュメント整理や、その検索方法など「必要なものをいかに簡単に取り出せるか?」を身につけることで効率が上がり生産性も上がるとも書かれており、確かに資料の見つからない時やどこにあるのかわからないということがよくあり、時間がもったいないと感じることが多いので、地味だけど整理力は大事だと気づくことができました。
最終章では、AIの台頭という大きな変化にどう向き合うかが語られます。
著者は、AIを恐れるのではなく、自分の専門性と掛け合わせて活用することの重要性を説いています。
そして、日本の成長を阻む「批判の文化」に警鐘を鳴らします。
新しい挑戦に対して寛容でなく、批判する文化が、イノベーションの芽を摘んでいると指摘します。
これからは、批判ではなく「コントリビュート(貢献)」と感謝の文化を育てることが、個人と社会の成長に不可欠です。
今では当たり前になってきてる AI ですが、どう付き合っていくかを考える内容でした。
昨今AIは多種多様にある世の中で、これからも様々なAIが出てくると思われるが、AIではカバーできない専門性を上げていくことでうまく付き合い生産性を上げていくことが今後…いやすでに今求められていることだと思いました。
また、批判の文化については確かになぁーと思わされました。
本書を読んでて確かに日本は「責任」や「完璧」を求めがちだと感じますし、世間的にそういう批判的な話題を見る機会が増えたと私も思います。
SNS然りニュース然りいやでも目に見るので、正直最近げんなりしています。
コントリビュート(貢献)や感謝の気持ちを忘れてはいけないと感じさせられました。
まとめ
『世界一流エンジニアの思考法』は、単なる仕事術の本ではなく、私たちの「働き方」そして「生き方」そのものを見直すきっかけを与えてくれる一冊だと思います。
生産性の向上は、根性や長時間労働によってではなく、合理的な「思考の習慣」と、心身のコンディションを整える生活習慣、そして互いを尊重し合える文化が生産性の向上につながります。
本書は、その普遍的な真理を、説得力のある実体験とともに教えてくれる書籍でした。
もし私と同様に、
- 日々の業務に追われ、成長実感を得られていない。
- 生産性を上げたいが、何から手をつければいいかわからない。
- より楽しく、主体的に仕事に取り組みたい。
と感じているなら、本書は良い書籍だと思います。
まずは小さなことからでも始めてみてください。
例えば、
- マルチタスクをやめて、タスクを1つに絞ってみる。
- 自分の時間をまずは1、2時間確保する。
- コミュニケーションの情報量を減らす。
- 瞑想・睡眠・ディスプレイから意識的に離れてみる。
- 筋トレ・有酸素運動する。
一つ一つはすぐにでも実践することが可能ですし、些細なことでもコンディションや生産性は変わります。
自分に合わなければ自分なりの方法を模索すればいいだけですからね!
興味を持たれた方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

![devlog [開発部門ブログ]](https://devlog.neton.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/logo.png)